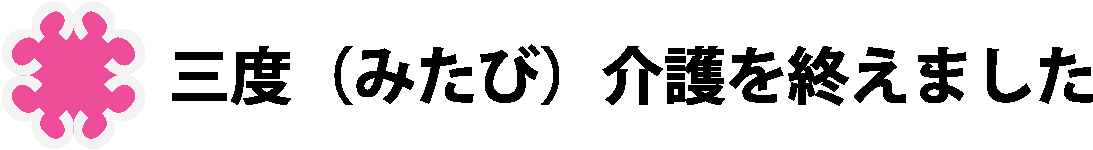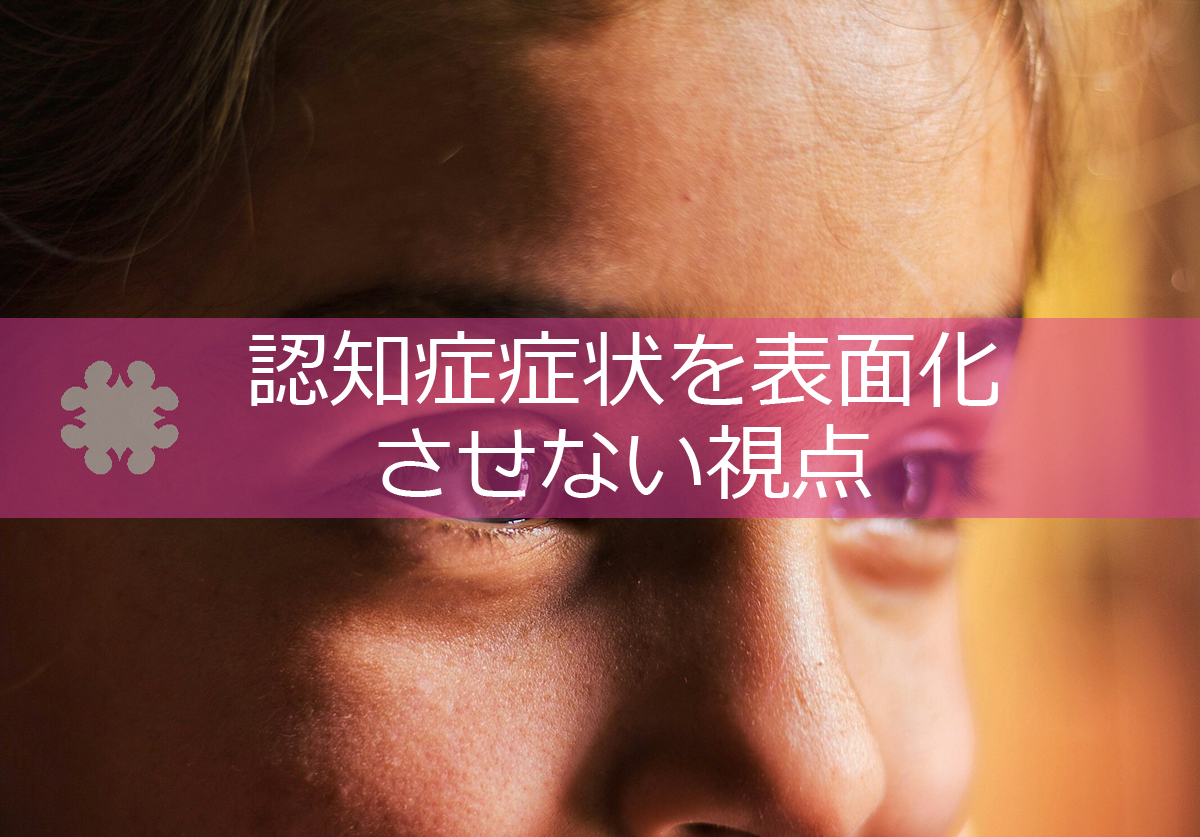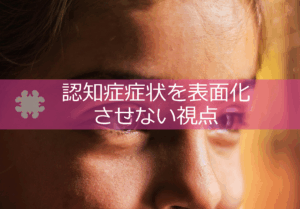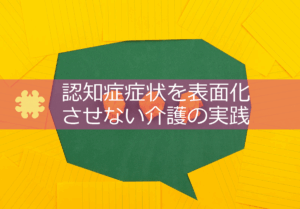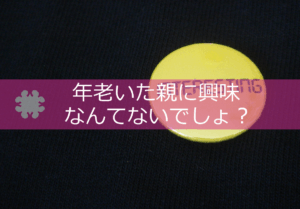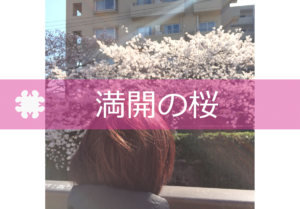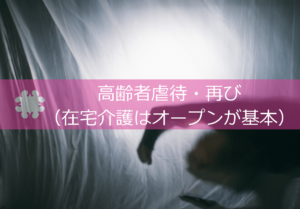認知症を患うとこの世の終わりだ!みたいな先入観はまずおやめになったほうが賢明です。
認知症にも種類があるので全てに当てはまるわけではありませんが、認知症を患った親を介護してみると最初に直面するのは、日によって状態が大きく異なるのに気づくはずです。
ある日は、昔からの普段通りの様子に見受けられたかと思ったら、翌日には不穏となる。最初は、不思議でした。ただ、そのうち判ってくるのが、誰でも日によって、好調、不調はありますね。それが認知症を患うと少々、独特になるだけです。
実は、このように判断できるようになる観察が、認知症症状を表面化させない視点なのです。
ひとりの認知症患者を24時間、365日つきっきりで観察
年老いた親御様の在宅介護において、非常に残念なこの世界の価値観は、その行為に何ら意味が無いかのような認識がはびこっている点です。
今、認知症の予防、改善に向けた医学的なアプローチは盛んです。
でも、どのアプローチも脳という人体の物質の疾患に対して、薬という物質でのアプローチがほとんどのように見受けます。もちろん、私の狭い了見なので、間違いかもしれないのはご了承願います。
しかしながら、そのような研究者は、ひとりの認知症患者に対して、どの程度の時間を接し、観察し、ノートしてきたのか。
24時間、365日をずっと一人の認知症患者に対して観察を続けているのか。
もっといえば、ひとりの認知症患者に対して、その研究者はどのような関係性なのか。他人なのか、親族なのか、それとも親子なのか。
認知症症状の観察で、その患者をとりまく環境が異なると、表面化する認知症症状も異なります。
例えば、年寄りを老害でしかないぐらいにしか思えない介護士が、いやいやで仕事だから仕方ないと、ある老人のお世話をしていれば、その感情は嫌というほどその老人に伝わります。その老人が認知症であれば、その人に対する不信感をうまく表現できずに、怒りっぽくなったり、不穏になるのは当然です。
つまり、人体物質の疾患に対して、薬という物質によるアプローチではなく、人体物質の疾患であっても対人の関係性に基づいて、疾患を持った人の心に深くダイレクトに働きかけるアプローチのほうが、よほど認知症症状を表面化させない効果があるのではないか。
要は、認知症は完治できないのであれば、認知症症状を表面化させなければ良い。
これが、私の認知症ケアに対する見解ですが、ここに至るまでには、実母と私という人間関係において、実母をひとりの認知症患者としても観察する視点を忘れず、24時間、365日つきっきりで見続けてきた結果なのです。
このような観察をとことんできるのも、年老いた親御様の在宅介護のものすごい価値ではないか、というのが私が強く持っている主張です。
なぜなら、多くのみなさんは、認知症を恐れているのですよね!?
治らないものを治そうとするアプローチは意味が無い
いまのところ、認知症は治らないと言われています。
いつか完治できるかもしれないのであれば、それは研究者のリサーチにお任せするとして、在宅介護の責任を担うと立場では、「治らないのであれば、どうするのか?」という視点が不可欠になります。
その視点は、認知症を患った親御様と一緒に暮らしても、その暮らしがとても楽しい、となれば良いのです。
年老いた親御様の在宅介護では、この視点が抜け落ちていると苦労の連続しかありません。
ネットでも、テレビでも報じられているのが、在宅介護の暗~いイメージを植え付けるかのような切り取りです。
私から言わせれば、意図的であり、阿保らしい映像にしか思えません。
上述しましたが、在宅介護には価値があります。
どのような価値か。
それは、≪ 生きるとは何か? ≫、それを如実に知るチャンスだからです。
この記事を読んでくださっている貴方様にお聞きします。
≪ 生きるとは何か? ≫
こんなことも判らずに、学校に通い、仕事をして、子育てして、いま介護に直面しているわけではないですよね!?
生きるとは老いて病となり死んでいくプロセスでしかない
老いていく親のお世話をしていると自ずと判ることであり、自分も含めて例外がないのです。
だからこそ、そこには虚しさしかないのが見えてくるはずです。
日付すらも判らなくなっていく現実が、生きる正体そのものだと理解できるはずです。
それが、在宅介護です。
ところが、プロパガンダは、介護作業が介護だと報じます。
これはものすごく狭い了見でしかありません。
在宅介護は、この虚しさしかない生きるプロセスの渦中に親御様を支える、という視点を欠いていては始まらないのです。
では、虚しさを支えるとは何か?
その答えは、簡単です。
助けてあげることです、イコール、介護する子が助けてもらいます。
例えば、認知症を患った親御様に自分を産んでくれた時の気持ちを尋ねてみたことはありますか?
認知症を患っていたとしても、親御様は、とても楽しそうにその時の気持ちを語ってくれるはずです。
楽しかったこと、苦労したこと、どれも微笑みながら教えてくれるはずです。
それを聞いた介護する貴方様は、チャンスを持つはずです。
≪ 産んでくれてありがとう。 ≫
この言葉を親御様に差し上げても、減るものは無いはずです。
本当の意味で助けるというのは、結果として自分が助けてもらいます。
それは、こういうことなのです。
同時に、その感謝の気持ちが在宅介護の出発点であり、認知症症状を表面化させない視点として欠かせないのです。
助けているようで、自分が助けてもらっている。
年老いた親御様を在宅介護でお世話していると徐々に判ってきます。最期の最期まで、親は親なんだと、私がまだまだ返さなければいけない恩を受け取らずに、この世界から去っていきます。
なので、どう助けるのか?
在宅介護の日々で、この創意工夫を日々、持ち続ける努力を重ねていく。そうすると認知症なんて、恐れるに足らずと判ってきます。
更なる結果として、このような私の経験を多くの人に知ってもらうことになる。その多くの人に、私が助けられています。