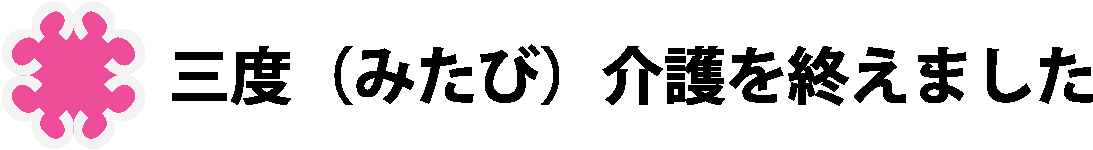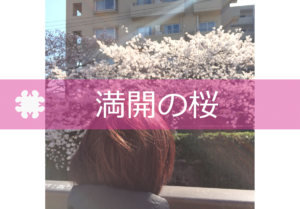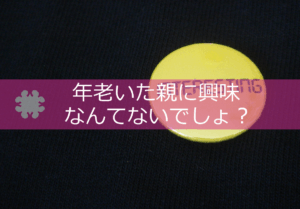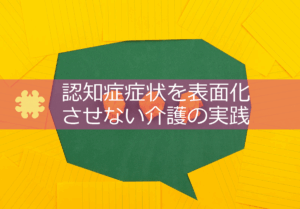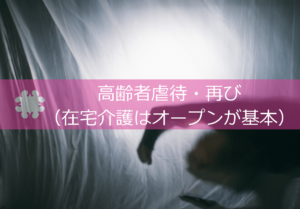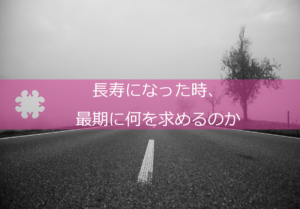認知症を患って要介護3と聞くと、どのようなイメージを持ちますか?
老後に一人で暮らすのは、ちょっと難しいかもしれません。なので、年老いた親御様を在宅で介護するようになります。
しかしながら、コミュニケーションが取れなくなるかといえば、十二分に可能です。コミュニケーションが取れれば、普通に親と子の暮らしが成立ちます。
でも、それが出来ないのはなぜか?
認知症により要介護3であった私の母とのコミュニケーションから解き明かしましょう。
認知症を患った親御様とのコミュニケーションの基本
今日は何月何日かと聞かれて、ちょっと「あれっ?」となる時は、誰でもあります。
その時、考えますよね。
カレンダーを確認しようとするかもしれません。
脳を使うわけです。
アルツハイマー型認知症に罹患すると、脳が委縮します。
使いたい脳が上手く機能しないので、日付がわからない、カレンダーをみても今、何年何月かもわからない。
年老いた親御様がそのような状態に陥った時、周囲にいる介護する人や、家族の反応は、どのようなものか?
容易に想像できますね。
表情は、あきれ顔かもしれません。
または、そのようなことも判らないのかと怒りに満ちた表情をしているかもしれません。
言葉は、非難めいたフレーズが出ているかもしれません。
介護する家族の気持ち、雰囲気、表情、口角は、攻撃的になっている可能性も強いです。
さて、このシチュエーションを一歩引いて観察してみると面白い構図が判ります。
年老いた親御様は、脳を使って答えを導き出そうとしているのですが、認知症によりそれが出来なかった。
一方で、介護する家族は、出来ない親を怒りの感情をあらわにして痛めつけている。
このような構図を観察できます。
そして、この構図から理解すべきは、人間としての未熟さの問題が誰にあるのか。
いうまでもありません。
怒りの感情に飲み込まれている介護する家族の側にあるのが明確です。
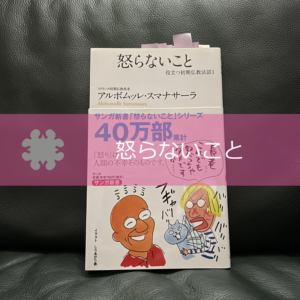
よく認知症患者には怒ってはいけない、とよく言われます。
このようなフレーズだけが独り歩きするので、介護する家族はストレスばかりを溜めこみ、在宅介護の価値が見出せないままなのです。
年老いた親御様が、日付が判らないという現実に対して、どう対処するのが理性的か。
これをキチンと分析し、自分のものとして実践できるようになるのが、認知症を患った親御様とのコミュニケーションの基本になります。
その話題は本当に必要でしょうか?
認知症を患った親御様の出来ることと、出来ないことは把握しているでしょうか?
ポイントは、状況毎に分けて分析するところにあります。
トイレ、食事、コミュニケーション、外出、・・・。
日常は、さまざまな活動があるのは言うまでもありませんが、何が出来て、何が出来ないのかをキチンを分けておくのは役に立ちます。
例えば、トイレでは、大便と小便とがありますが、それぞれ用を足すのにどこまでが出来て、どこが出来ないのか。
その把握から、介護する範囲が決まります。
さて、この記事では、コミュニケーションを取り扱いますが、相手と会話がキチンと成り立つサブジェクトと、全く成り立たないサブジェクトがあります。
実は、これ、相手が認知症の有無とは関係なく、50代の男性と20代の女性との間で成り立つ会話を考えてみても同じなのです。
50代の男性は会社組織内の競争について話したくても、20代の女性には興味がないかもしれません。
逆に、20代の女性はネイルについて話したくても、50代の男性には興味がありません。
この状況と同じように、認知症を患う年老いた親御様と、介護する家族との間で成り立つ会話もできるだけお互いに興味を持てるサブジェクトで会話を重ねるようにします。
例えば、日付なんて、年老いた親御様が、ばっちり理解しておく必要がありますか?
介護する家族が把握していれば、まったく必要がありません。
にもかかわらず、日付が判らなくなるのを問題視してクローズアップしすぎるのです。
それよりも、食事を一緒にしているのであれば、美味しさを会話のサブジェクトにする。
その美味しさから、昔を思い出すならば、その思い出を深堀するコミュニケーションを重ねる。
要は、認知症を患っていたとしても、積極的に言葉やフレーズを発してもらうように、促していく。
これが認知症を患った親御様とのコミュニケーションのコツになります。
もう一度、言ってみて!
例えば、認知症を患った親御様の人生最大のピンチは、いつだったのか?
介護する子として、ここまで育ててきてくれた歴史の中で、親の苦労を知る機会になるかもしれません。
介護する子が生まれる前、父と母はどのような暮らしをしていたのか。
認知症を患っていたとしても、発語ができるのであれば、いろいろと話をしてくれるはずです。
そして、介護する立場の家族が知らない話も出てきます。
これは学びになります。
ですから、そのような時は、スマフォの動画撮影をオンにして、次のように言います。
「もう一度、言ってみて!」
特に、自分が生まれる前、両親にはどのような時間が流れ、自分を産んでくれたのか。
多くの人の歴史は、中身の全くない学校で習ったものが共通認識のはずですが、両親が知り、感じ、生き抜いてきてくれた歴史こそが、本当に自分が知らなくてはいけない歴史であり、それが両親の心には眠っています。
本当の歴史の学びは、自分が生まれる前の両親の心に眠る記憶を出発点として、当時の地域、日本、世界の状況、さらにそれ以前へと遡っていきます。
今ではイイクニツクロウというのは怪しいと言われてますが、そんなものは合っていようと間違っていようと意味がありません。
どのような礎のもとに自分が生まれたのか。
それを理解し、それを活かすのが本当の歴史教育であり、それはずっと一緒に暮らし、在宅介護のお世話を通じて心を通わせる親からマスターするのが出発点です。
外交では、歴史認識や、歴史問題がクローズアップされる時が多々あるのは、ご存じのはずです。
しかし、本当に学び、活かさなければいけない歴史は、親御様の心に眠っています。それを引き出して、自分のものとしたとき、ルーツ、すなわち確固たる礎ができます。ひとりひとりのその礎の集合知が、本当の日本史です。
それは、誰にも改ざんできるものではありません。上っ面の何年に何が起きたといった単なる情報が歴史認識だから、テキトーに改ざんされてしまいます。
在宅介護は、自分にとってマスターすべき歴史を学ぶキッカケに出来ます。