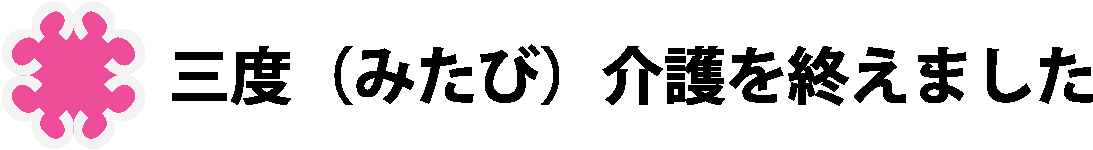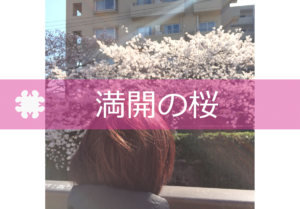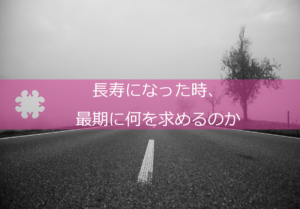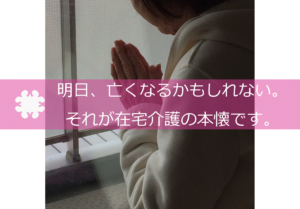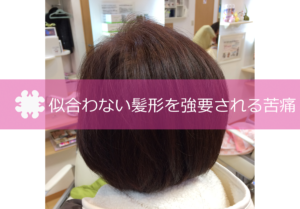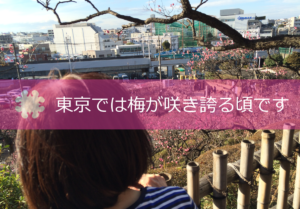在宅介護の真っ最中は、その日を乗り切っていくのに全力投球になります。
そのため、昨日を振返る、1週間前を振返る、そのような余裕はありません。
私が、回顧録として介護経験をまとめているのは、一つの出来事をキチンと振り返ることのできる、そのメリットを最大限に活かしたいため、というのも判ってきました。
なぜなら、ある出来事は、その時に意味や価値が判らなくても、時間が経過することによって、点としてではなく、線を形成する要素として見えてくるからです。
在宅介護は、今に集中しますが、それがどのような意味を持ってその後の人生に良い影響を及ぼすのか。その観点をご紹介します。
喪失
いま、この記事を読んでくださっている方は、おそらく親御様の介護に一生懸命に取組んでいらっしゃるのではないか、と想像しています。
介護をやる前と違って、やってみて初めて判ることがたくさんありますよね。
例えば、なんとか健康状態が良くなるように介護をして、結果として良かったと思える日があっても、次の日には、また悪くなる・・・。
支えても、支えても、支えたところは何とかなったとしても、他がダメになってしまう・・・。
そして、徐々に、徐々に、健康を失っていき、3カ月前はおろか、2週間前の健康状態にさえ戻らない。
よく介護は終わりが見えない、そう言う人がいらっしゃいます。
見も蓋もない言い方をして申し訳ないのですが、年老いた親御様の介護は、親の死で終わります。
ですから、終わりが見えないというのはあり得ないのですが、支えても支えても支えきれない感から終わりが見えない、という気持ちになるのも無理はありません。
というのも、老いていくプロセスは、若いときには理解できないスピードで「喪失」が促されていきます。
健康だけではありません。
モノもそうです。
人間関係もそうです。
親子であっても、その関係性には終わりに向かう減算していく時間が含まれています。
それらは、すべて「喪失」していきます。
さようなら。その連続です。
前の記事で、親族による母への虐待について記事をアップロードしました。
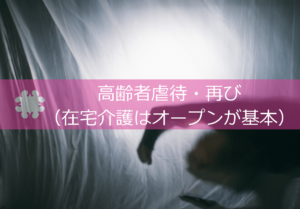
このような行為がなされた時も、その時は憤りしかありません。
しかし、いま振り返ってみれば、遠い昔の出来事で、ハエが部屋を飛び回っている程度の煩わしさしか感じません。
その遠い昔の出来事も、今にとってみれば、「喪失」の線の上にあるごくわずかな点でしかないのです。
具体的には、母と、その親族の縁が薄まり、切れかかり、無くなっていく。
これを如実にきびしく体感させ、振返りで気づきとなって自らの糧となっていきます。
今日も、あらゆる人、物、出来事が目の前を去り、消えてきます。
さようなら、その連続です。
喪失が生きる姿
私の両親、そして配偶者の両親、合計4人の親が居ました。
私の父親は、私が若い時に他界しましたが、他の親は長生きしてくれて、最近にお別れとなりましたが、どの親も病院で看取ることとなりました。
最後の入院となるときに、これまで住んでいた家の玄関を出ていきます。
その時は、最後になるとは思っていないのです。
でも、最後に家の玄関を出てきます。
一緒には、帰ってこれないのです。
帰らぬ人になります。
これまで雨風をしのいで、食事をして、寝起きのあった日常生活がその家からなくなります。
この喪失感は、もう味わいたくない。
しかし、その思いは叶いません。
喪失が、生きる姿であり、老いだとわかるから、苦でしかなくなります。
春は、私の母の命日なので、当日のことを思い出します。
若い頃は、得ようとして頑張ります。お金、仕事、配偶者、地位、子、名誉、・・・。しかし、喪失の連続が生きる姿だと判ってしまうと、その対象への興味はセピア色へと変わっていきます。
だからといって、努力しないのではないのです。よりクオリティ高く仕事をしよう、生活費は頑張って稼いでいこう、配偶者をはじめ、周囲の人には親切にしよう、立場があるならその責任を全うしよう。この日常に変わりはありません。
しかし、その時がくれば、「さようなら、ありがとう。」未練を残さない生きかたへと在宅介護の経験は導きます。