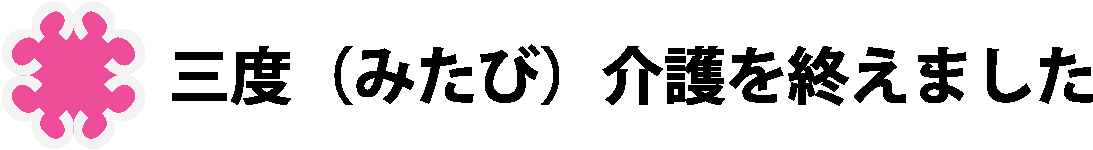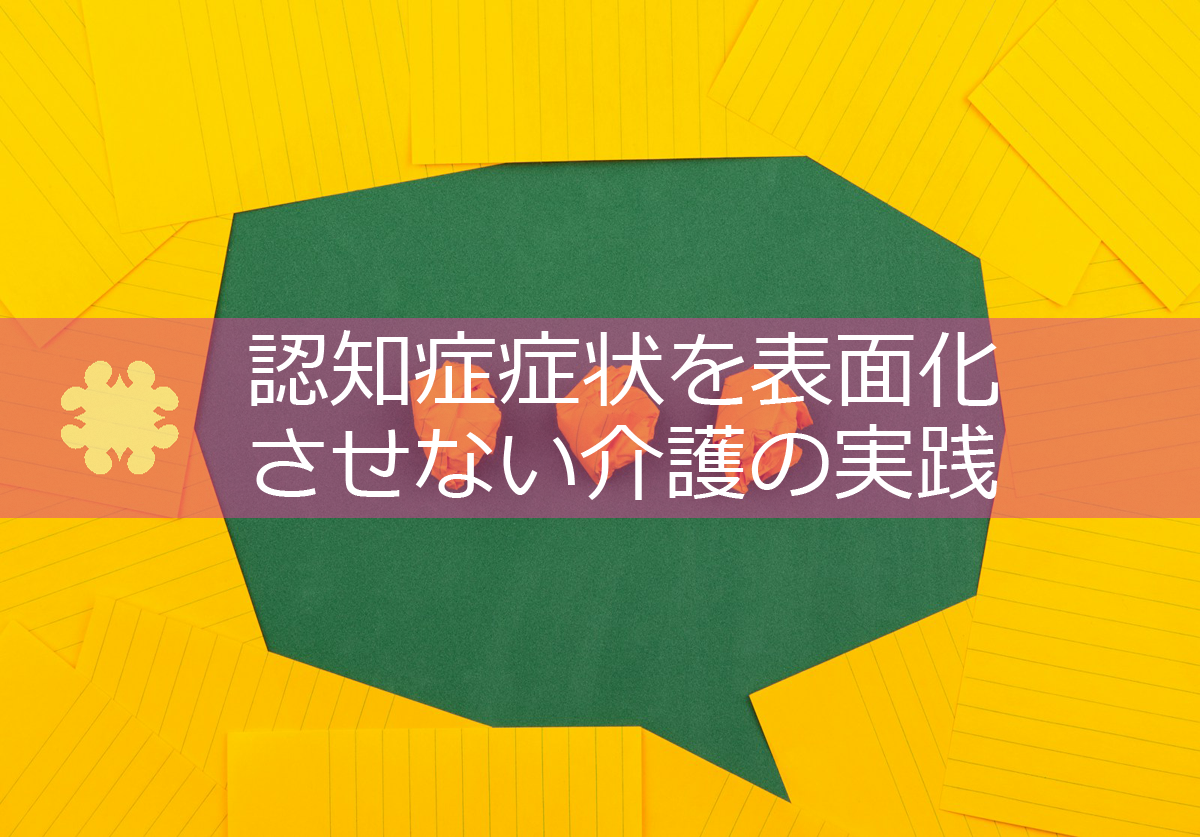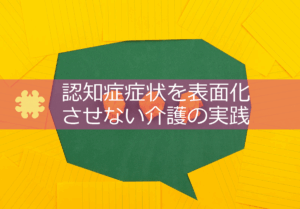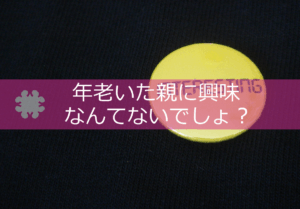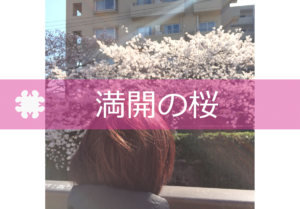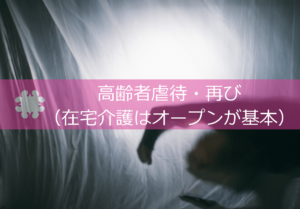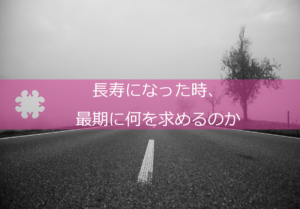私は、認知症に罹患しません。さて、そう言い切れる人は、いらっしゃるでしょうか?もちろん、将来のことですから、そのような保証はありません。もし、私が認知症に罹患したら大いに笑ってやってください。
しかしながら、認知症に罹患してもしなくても、あまり恐れる必要はないというのが私の経験則です。なぜなら、認知症は、脳の疾患であって、心は認知症にはなりません。
心がしっかりしていれば、コミュニケーションも難しいものではない。認知症を患った実母の在宅介護実践と観察結果です。
その理由?簡単です。コミュニケーションの基本は、「心を通わせる」。これに尽きます。
認知症症状を表面化させるから問題が生じる
例えば、日付が判らなくなる。
認知症によく見受けられる症状です。
そして、それではマズイ、と考えるのが世間の見方です。
そのため、日めくりカレンダーなど導入していませんか?
実母の在宅介護が始まった当初、私の家庭でも導入していました。
でも、導入して日めくるかと言えば、めくりません。
三日坊主で終わります。
それで、どうしたものか・・・、と思うわけですが良いアイデアがありません。
 さくら
さくらそもそも認知症で判らなくなったものを判るように出来るのか?
ある日、そのような疑問を持ちました。
なぜなら、認知症は治らないと言われているのはご存じの通りです。
 さくら
さくら日付が判らなくて、日常生活に問題はあるのか?
確かに、長寿を迎えて一人暮らしであれば、日付がわからないのは問題になるでしょう。
しかし、在宅介護で、家族の誰かが親の傍にいるのであれば、問題は生じません。
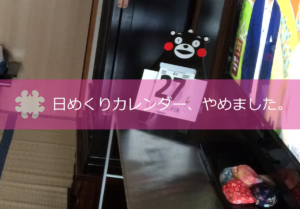
日めくりカレンダーを辞めました。
というより、『今日は何月何日?』などと尋ねる行為を一切、やめました。
話題から日付を無くしたのです。
もし、日付を話題にしなくてはいけないケースでは、私から『今日は何月何日なんだけどさぁ、明日の通院の時間が何時頃だから・・・』といった感じで、母に日付を考えさせる行為をやらせないようにしました。
よく考えてみていただきたいのは、認知症を患って日付が判らなくなって、『今日は何月何日?』と尋ねられた時、ストレスになるのか、ならないのか。
答えは、ストレスになります。
それも、かなり強いストレスになります。
そのため、親は認知症を患いながらもなんとかしようと試みますが上手くいかない。
介護する子から見れば、それが認知症を患った親の問題行動に見えてしまうのです。
認知症症状を表面化させない考え方
よく観察していると判るのですが、日付ぐらいは簡単に判っていなくてはいけないという意識は、認知症を患った本人が最も良く判っているのです。
ところが、認知症を患った本人はよく判らないので、困り、ストレスを貯める。
このようなネガティブ・スパイラルを回避するために、判らないことを判らないとして、コミュニケーションから除外する。
結果、ストレスフリーとなり、心に余裕が生まれます。
まず、このように心の余裕を持ち続けてもらうのが、認知症症状を表面化させない考えの根本になります。
年老いた親御様の気持ちを十二分に引き出して差し上げる
さて、簡単に書きましたが、心の余裕を持ち続けるというのは、容易に出来るでしょうか?
在宅介護で頑張っている人を見ていますが、基本的に年老いた親御様をどうにかしようと言葉をかけるなりしてコミュニケーションしているのではないでしょうか?
要は、介護する子が、親に何かを期待してコミュニケーションする。
この状態が、多く見受けられます。
例えば、トイレ介助の実際を見てみましょう。
認知症が進行すると、自分でトイレを済ませるというのも大変な作業になります。
それは、親御様がもっともよく理解しています。
認知症を患っているとしても。
そこで、介護する子は、トイレが少しでも自分で出来るようにと親に期待してコミュニケーションするはずです。
でも、期待は裏切られるはずです。
しかし、それは、当然です。
そもそも、親だって、自分で用を済ませるようにしたいけれど、それが出来ないで自分自身が困っているのをよく知っています。
ましてや、トイレ介助なんて、子に手伝って欲しいなんて思う親は居ません。
その親の気持ちを融解させるところから始めないと、トイレ介助は、そう上手くはいきません。
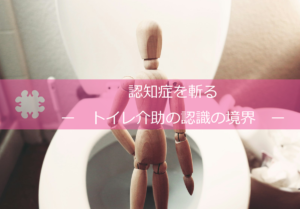
トイレ介助に限りませんが、在宅介護が始まった当初、母に次のように伝えています。
 さくら
さくらお母さん、私はね、お母さんの介護をやりたいと思っているから一緒に暮らしているんだよ。
また、三度目の在宅介護となった岳母には、次にように伝えています。
 さくら
さくらお義母さん、いいですか、申し訳ないとか言って遠慮しちゃダメです。堂々と介護されてください。
どの親も子に迷惑をかけたくないと思っていますから、その気持ちを手放すようにコミュニケーションする。
それが、親自身が心の余裕を持てるようになるスタート・ラインです。
在宅介護は大変です。自分の時間、仕事、経済力、精神力、人間関係などなど、失っていくもの、無くなっていくものは多大、そんな風に思うはずです。事実として、そのような側面はあります。
しかし、どれも復活できるものばかりです。失うばかりに目を奪われれば、それに囚われ、回復できません。立ち位置が違うのです。
在宅介護経験は、自分に対する最高の投資だという認識を持っている人はまず居ませんからね。この気づきができるかどうかも在宅介護経験が宝となるか、クズとなるかの鍵です。