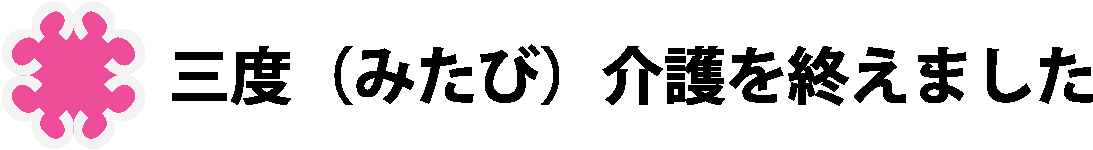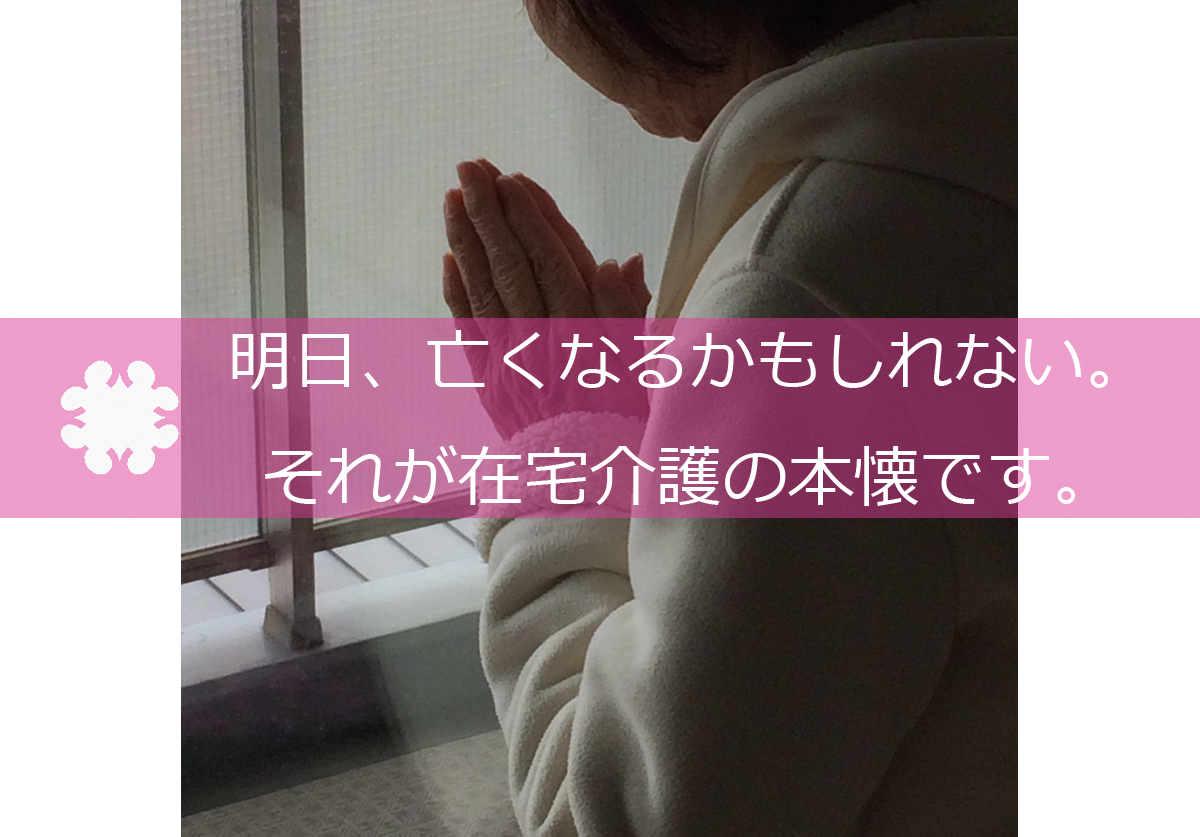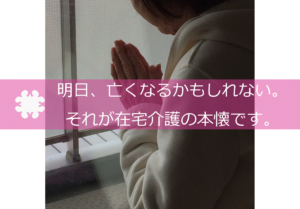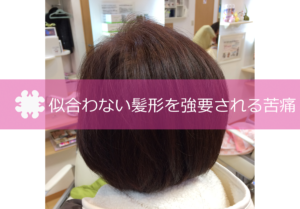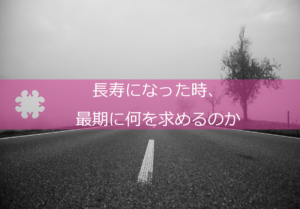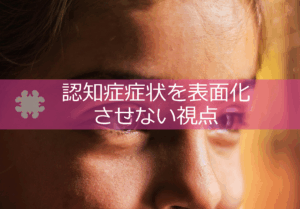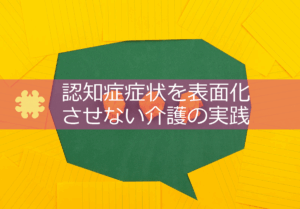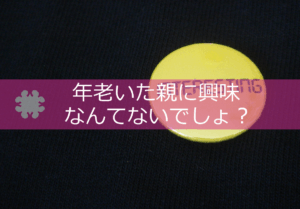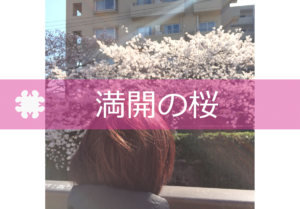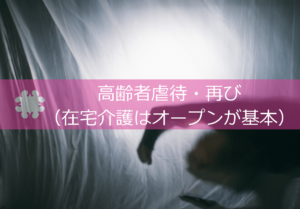明日、亡くなるかもしれない。
大切な人とのお別れは、必ずやってきますがこの感覚を切実に持ち合わせている人は非常に少ないし、言われてもピンとこないはずです。当たり前ですが、多くの人にとって、自らの死さえ誰かの遠い未来のイベントぐらいにしか思えていないのですから。
しかし、この感覚を研ぎ澄ませてくれるのが、在宅介護の本懐です。
逆に言えば、親御様の在宅介護を最期まで完遂した人は、この感覚を備えています。そのため、在宅介護をキチンと全うした人は、誰に対しても、今、この時、今日、この日を大事にして接する能力をナチュラルに備えます。
死を遠ざけず、明日に近づける取組が在宅介護
もし、在宅介護の責任を担っていらっしゃっているなら、親御様が明日に亡くなるとしたら、今日をどのように過ごすでしょうか?
在宅介護に限りません。
家庭の中でも同じです。
大切な配偶者が、明日にも亡くなる。
大切な子供が、明日にも亡くなる。
大切な親、きょうだいが、明日にも亡くなる。
もし、明日にも大切な人が亡くなるとすれば、今日をどのように過ごすでしょうか?
その今日は、必ず生じています。
馬鹿にしているの?
ある日、デイサービスから戻ってきた母が私に伝えてきた言葉があります。
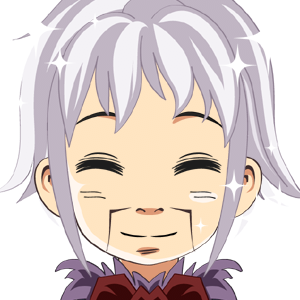 さくらの母
さくらの母あのような施設は、人を馬鹿にしているのか?
当時は、私も実際に介護施設で働いた経験が無かったので、判りませんでした。
でも、母の死去後、実際に介護施設で働かせてもらうとよく判りました。
同じ主旨のことを、施設を利用するご長寿の方々は、口にされていました。
そのたび毎に、回答に苦しみ、心苦しかった覚えがあります。
実際に、母が経験したことは、レクリエーションでクリスマス(12月)、お正月(1月)、そしてひな祭り(3月)というイベントで同じ材料で、同じ形状で、それぞれのイベントに沿って若干変化を加えた人形を作るというものでした。
母は、こうも私に伝えてくれました。
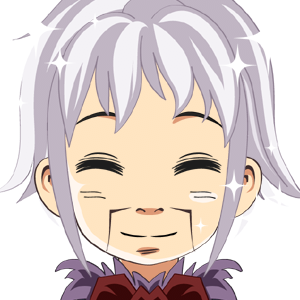 さくらの母
さくらの母あのさ。 確かに、認知症かもしれないけれど、何やったかぐらいはちゃんと覚えてるのよ。 短期間に立て続けに似たようなものを三回も作れば、誰だって嫌になる。
別れゆく大人の人と接する
このような問題が生じるのも、人を認知症患者として扱うのか、それとも別れゆく大人の人と接するのか。
その違いです。
よくSNS上で、施設利用者の生活状態を紹介しながら、施設職員の対処を紹介している記事を見かけます。
ただ、やはり、明日に別れゆく大人の人との接し方ではなく、認知症症状を患った人へ対処といった内容の方が多いように見受けます。
当然だと思います。
なぜなら、人はどう死ななくてはいけないのか?
教えられますか?
施設で働いている職員の誰もが、死にたくはないと思って仕事しているのに、どう死を迎えなくてはいけないのか、なんて伝えられないでしょう。
でも、ご長寿の方々は、残り何年も生きられるとは思ってもいないのですから、どう死を迎えなきゃいけないのか、その漠然としたサブジェクトに取組んでいます。
これが判っていれば、そのレクリエーション、明日にも亡くなるかもしれない人に必要でしょうか?
もっとも、どう死ぬのかは、あまり重要ではありません。
なぜなら、誰もが死に向って生きていますから、明日にもその時が誰にでも訪れる可能性があるだけです。
だからこそ、今、何をどうしますか?
これが問われるのです。
私の母が言ってくれた、「あのような施設は、人を馬鹿にしているのか?」という言葉は、≪ 今を生きる ≫、この大切さを問うています。
レクリエーションが無駄だとか、意味がないとか言ってるわけではありませんので、曲解はされないようにしてくださいませ。
介護施設で働いていた時のことです。
利用されるご長寿の方々とは、1対1になるとよく本音で話をしてくれました。これまで生きてきた時代、時間はその人とって非常に豊かなものです。それが、施設に入所したり、通ったりすれば、単に高齢者の一人として扱われるのが現実です。
認知症を患っていれば、施設の職員は、認知症患者というフィルターを通して接してこられます。
その人が、どのような人生を歩んでこられたのか。その人生への理解をどの程度まで深められるのか。
例えば、焼夷弾一発が近くで破裂した時の恐怖を語られた時、その恐怖を理解できそうですか?
その一発で大切な人を亡くした人の気持ちに寄添えますか?